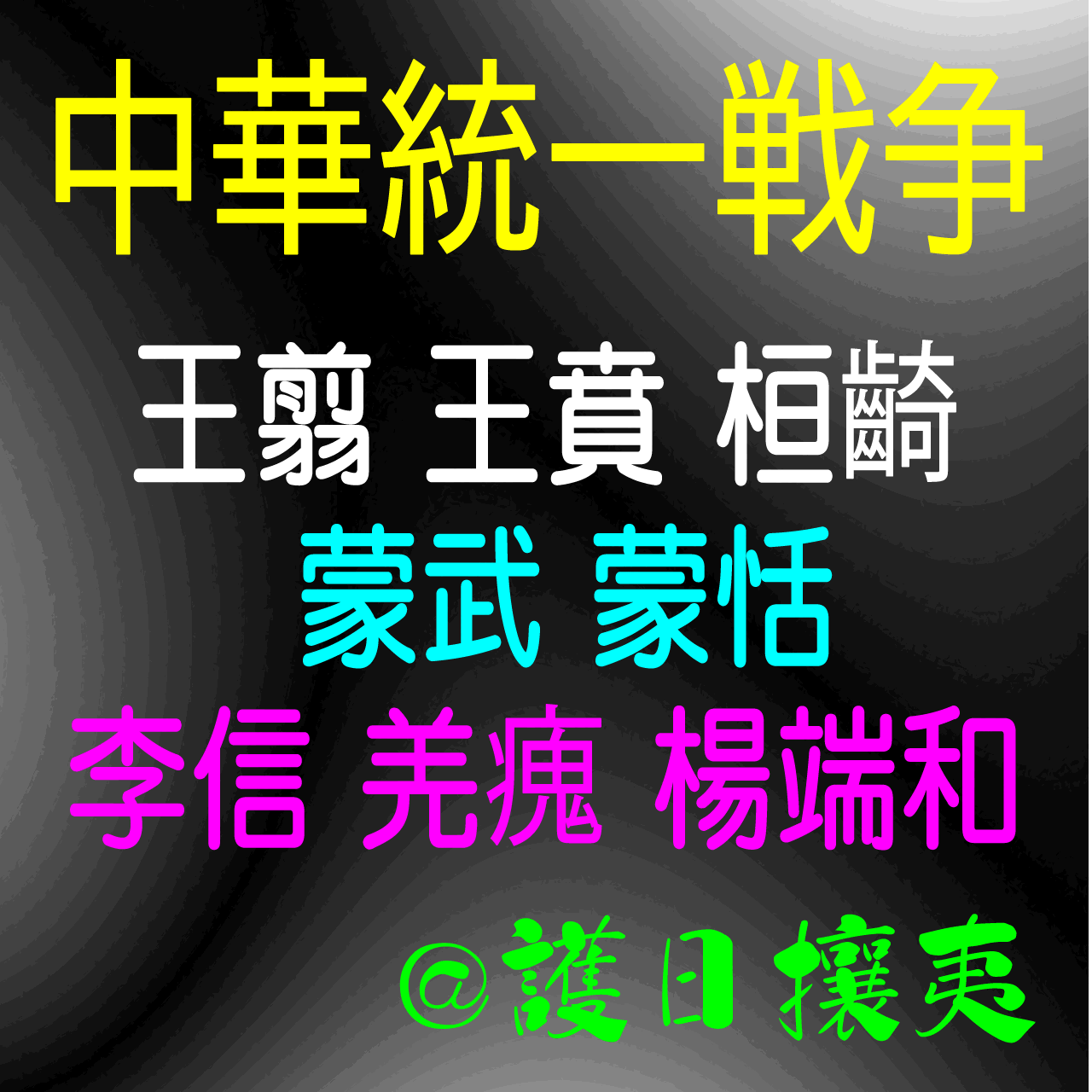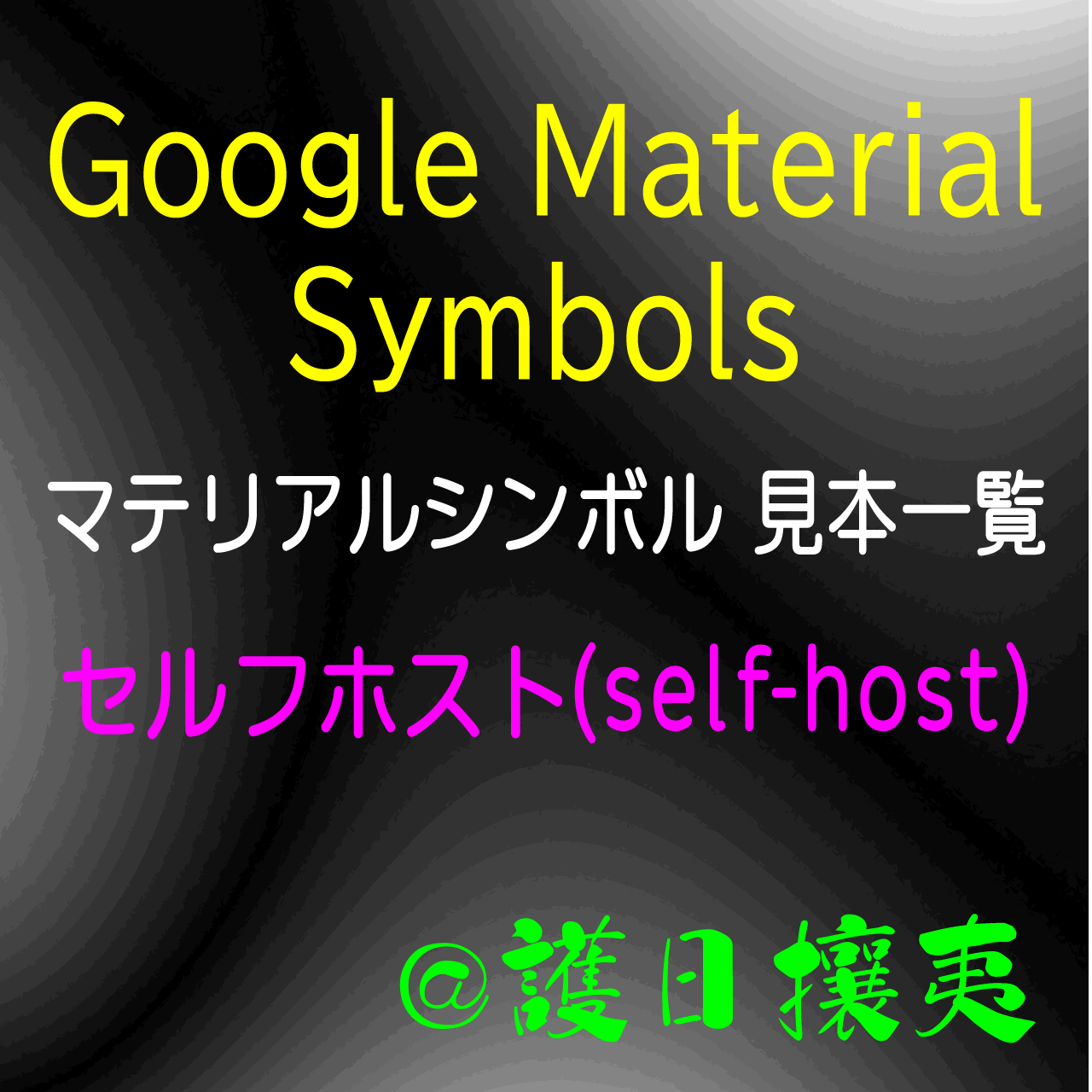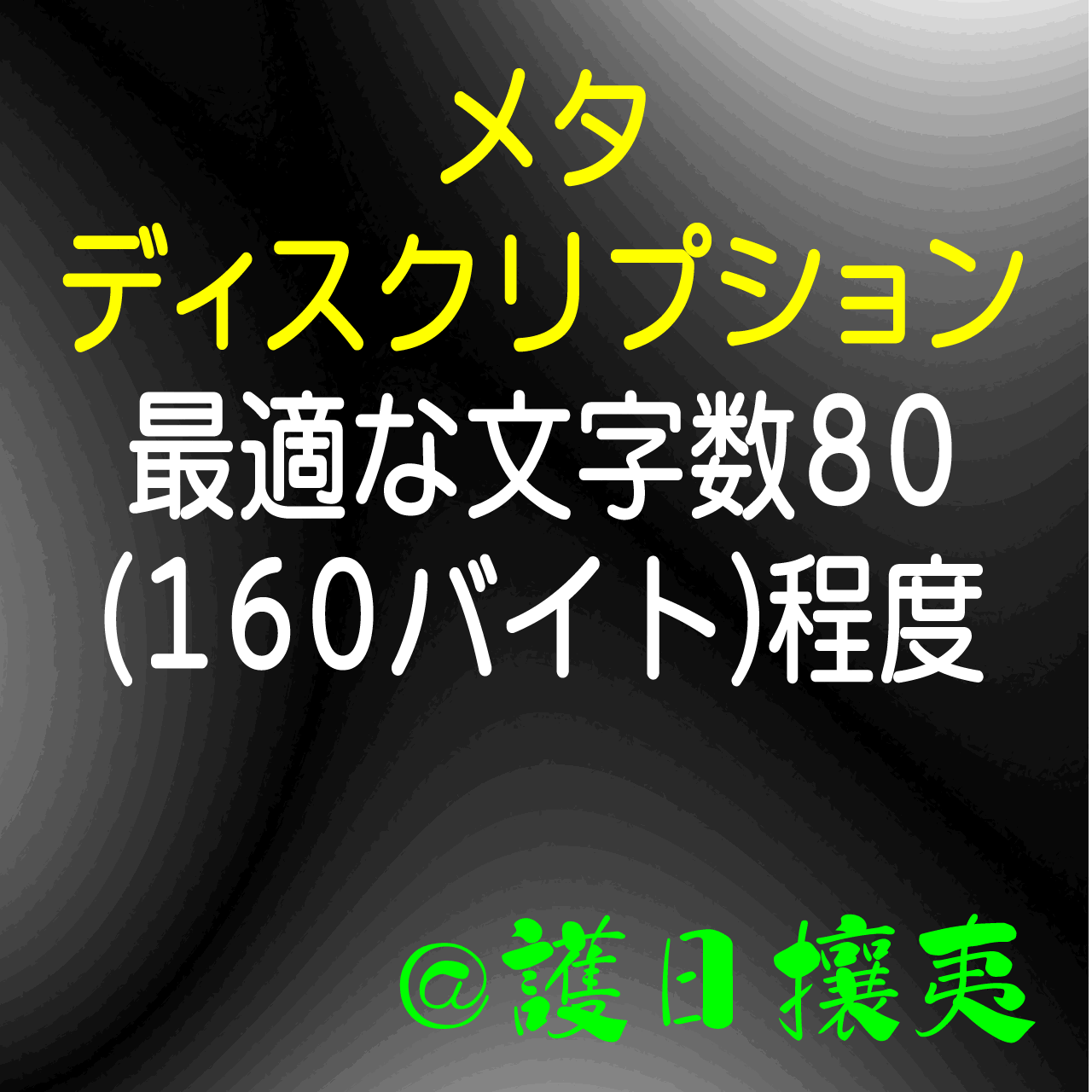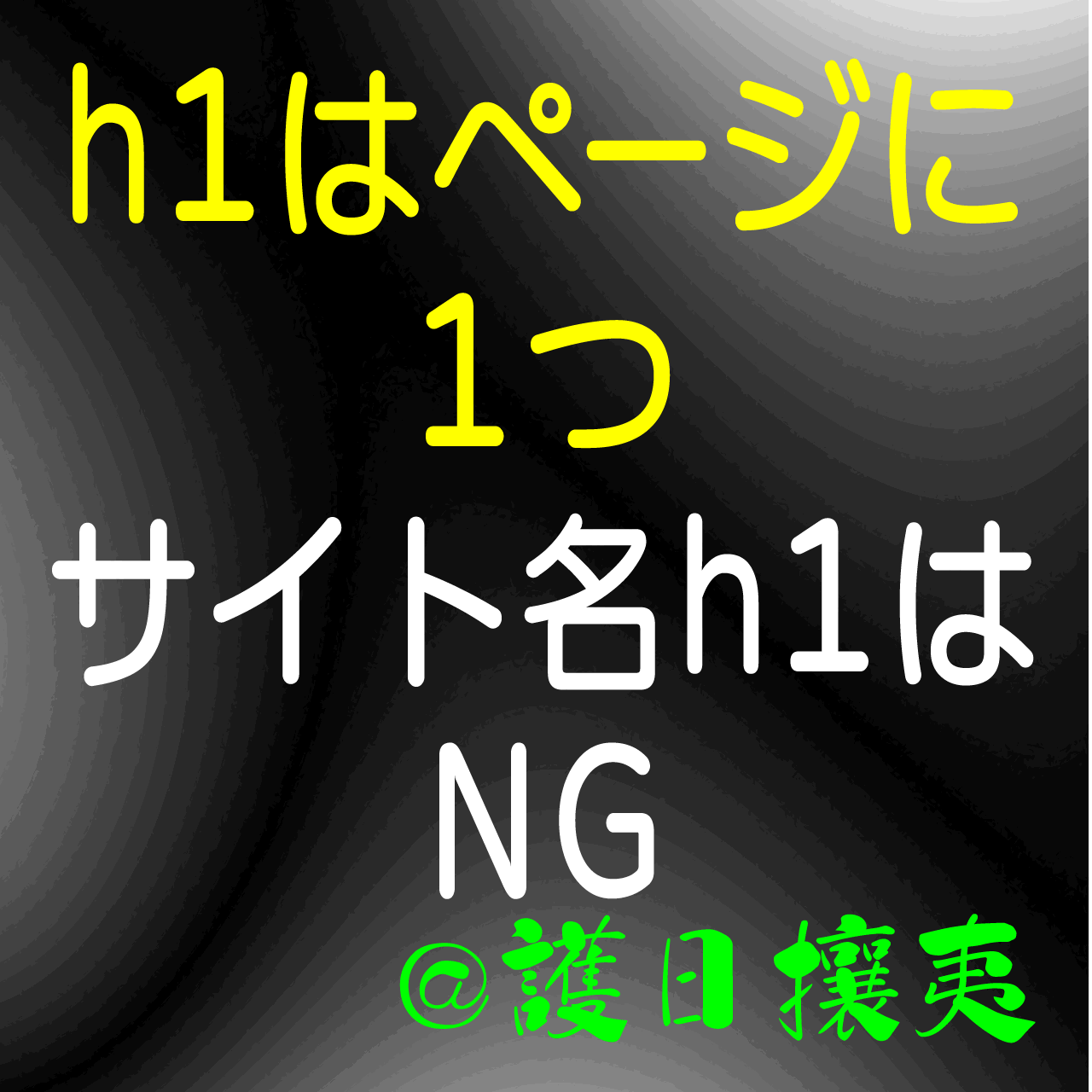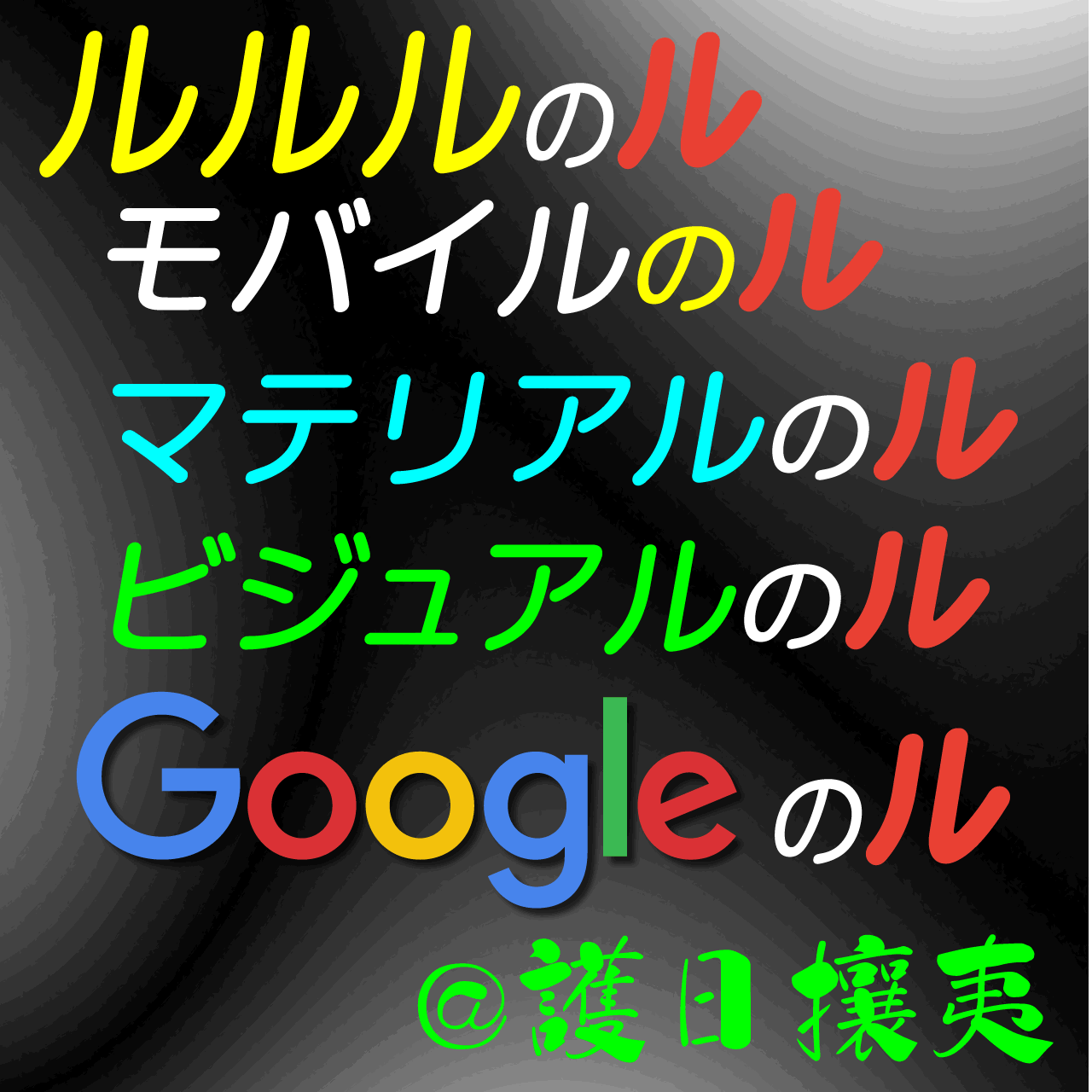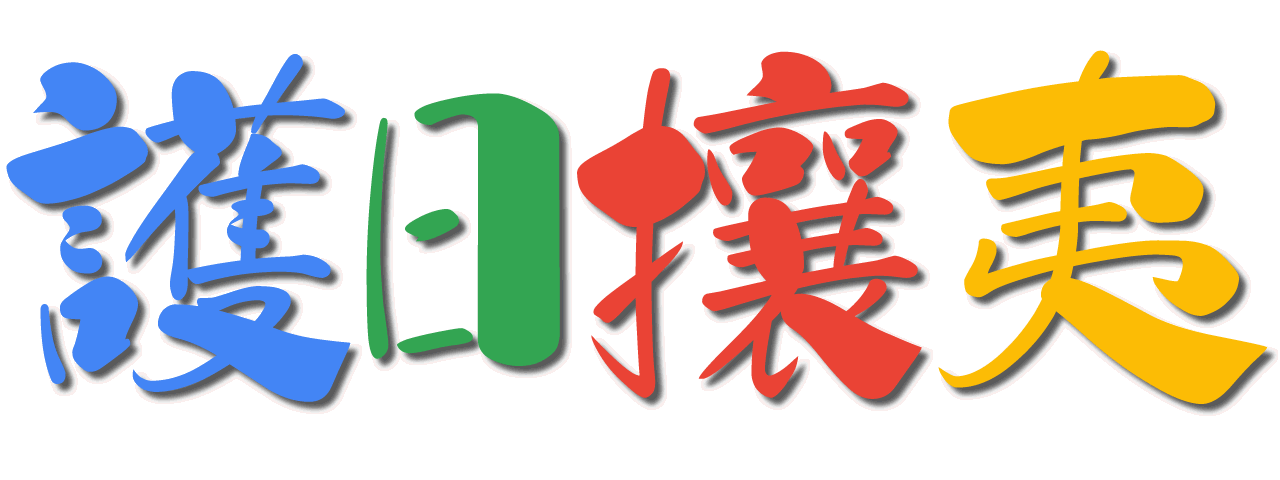【2024年最新トレンド】メディアクエリ ブレイクポイント range syntax併記
メディアクエリの一般常識
あらためて、メディアクエリ、ブレイクポイントの現在地をまとめておきたい
デバイスの振り分けとして~sp tb dt
AppleのiPhoneをはじめ、GoogleのAndroidなど、スマートフォンの普及が画期となっている
Web作成側ではスマートフォン sp、タブレット tb、パソコン(デスクトップ dt)で
はっきりくっきりすっきり あるいは 無難に、Webのサイトやページが表示されることが要求されている
デバイス画面の細分化~spY/X tbY/X dt
デバイス別の振り分け、大中小画面(ディスプレイ)ごとのWeb表示を細分化すると
スマートフォンの縦画面 spY、横画面 spX、タブレットの縦画面 tbY、横画面 tbX、デスクトップの画面 dt
このように仕分けできる
デバイス画面細分化の実情~tbY ≒ spX tbX ≒ dt
Web制作側としてメディアクエリ、ブレイクポイントの作業現場では、スマートフォンとしては縦画面 spY、タブレットとして tbY(spXを含む)、デスクトップとして dt(tbXを含む)
そして、spX ≒ tbY、tbX ≒ dt とみなす あるいは まとめて、スマートフォン・タブレット・デスクトップと表現していることが多い
アイコンであらわす場合も、つぎのとおり
作成側からも実機の普及度からも~タブレット無視?
弊社では、ブラウザーのデベロッパーツールの恩恵もあって、レスポンシブの表示確認は、スマートフォンの縦画面と横画面、およびデスクトップ画面で済ませるようにしている
つまりタブレット無視で、spY・spX・dt である
メディアクエリ ブレイクポイントの実数値(弊社)~600 960
そのデベロッパーツールを駆使して確認しているが、spYとspXのブレイクポイントは「600px」、spXとdtのブレイクポイントは「960px」にしている
「600 960」がブレイクポイントであり、それに沿ってCSSのメディアクエリを記述している
メディアクエリ ブレイクポイント 設定の根拠
あくまでも弊社設定では、スマートフォン縦画面と横画面の間で最初のブレイクポイント(600)を設定している
タブレットは無視して、そこからデスクトップへの切り替え(960)
スマートフォン縦画面から横画面のブレイクポイント
要するに、スマートフォンのディスプレイの縦画面の横幅は、最低がたとえば iPhone 5 おとび iPhone SE 2016 の「568」
そのほかは、800前後で900越えもあるが、最高が「960」
そこで、スマートフォンとの縦画面と横画面の境界値は、600に
568は、縦画面扱いとする
デスクトップ画面用へのブレイクポイント
デスクトップのブレイクポイントが必要なのは、ほとんどサイドバーの扱いで、多くのサイトはモバイルではサイドバーを折りたたんでいるはず
つまり、サイドバーを左か右に(あるいは両方に)表示するための、デスクトップのブレイクポイントということになる
極端には、デスクトップのブレイクポイントは、サイドバー表示のブレイクポイントと言うこともできそう
メディアクエリ不要がトレンド?
とはいうものの、メディアクエリが不要になるケース、メディアクエリを採用していないサイトが増えている
モバイルファースト~1カラム
スマートフォンの縦と横の画面、タブレットの縦画面は、おそらく1カラムで表示されることが多い
あるいは、それが定番
そこで、スマートフォン画面での表示を第一に考えると、デバイス間のビジュアル的断絶を意図的に回避するのであれば、デスクトップまでを「1カラム」にするべきだろう
実際、Facebookを除いてGAFAでは、デスクトップでも1カラムになっている
さらに、Microsoftも1カラム
画像~ブラウザーがレスポンシブ表示
画像は、サイズ(容量ではなく横幅)がどれだけ大きくても、ビューポート あるいは 画像格納のボックス幅に合わせて、ブラウザーが伸縮して表示してくれる
とにかく、CSSの最初のほうに、次のように記述しておけば、勝手にレスポンシブとなる
img { max-width: 100%; height: auto; }また、ブラウザーがアスペクト比を保って画像を伸縮させるために、イメージタグ(img)に width / height を記述しておくと、完璧である
レスポンシブコード~clamp vw calc minmaxなどなど
CSS3かCSS4か、最近のCSSは、関数のプログラミングコードが圧倒的に増えている
とくに、デバイスの画面やブラウザーの幅などのビューポートに合わせて、サイズを伸縮させる仕掛けがありがたい
これらは、ブラウザーが自動計算してくれるので、メディアクエリなしで、最初に設定しておけば、勝ってにレスポンシブとなる
flexboxマジック gridパラダイス
flexboxやgridは、コンテンツのパーツを自動でレスポンシブにするだけでなく、Webサイト・ページのレイアウトさえ自動レスポンシブにしてくれる
上記ページの下のほう、「Google のプロダクト」の親divでは
grid-template-columns: repeat(12,minmax(5px,1fr));このようなCSSが記述されている
縦に列を展開する、12回繰り返す、1つのgridアイテムは最低5px・最高自動計算幅、というコードである
もちろん、川上で「display: grid;」が設定されている
上記Googleのページでは、デスクトップで4列、タブレットで2列、スマートフォンで1列に表示されている
Material Symbols wght 100~700 サンプル
では、Material Symbols and Iconsの検証とはテーマが違ってくるが、grid minmax を試してみよう
grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(11.5rem,1fr));grid minmax は↑のとおりauto-fitが折り返しの万能コード
fluid_med
fluid_med
100
fluid_med
fluid_med
200
fluid_med
fluid_med
300
fluid_med
fluid_med
400
fluid_med
fluid_med
500
fluid_med
fluid_med
600
fluid_med
fluid_med
700
あえて枠線を設定してみると、お見事!
非常にくっきりはっきり、美しく整列している
gap や minmax の min最低数値がキモ
ブラウザーのデベロッパーツールでデバイス別の表示を確認すると、この grid minmax の最大の特徴は、レスポンシブで表示列が変化していくものの、それぞれ画像の大きさがほぼ同じになっている
これはこれで画期的な gridパラダイスかもしれない
grid minmax でもメディアクエリ採用
スマートフォンの縦画面や横画面で、列数を調整したいときは、メディアクエリで minmax の最低数値を変更すると、好みのカラム数にすることもできる
メディアクエリ無しブレイクポイント?
レスポンシブ関数CSSや、flexbox・gridとならんで、画像用の新しいレスポンシブコードも登場している
レスポンシブイメージ
下記ページなど、しどろもどろながら解説しているが
linkレスポンシブ問題 CSSピクセルとデバイスピクセル DPR(Device Pixel Ratio)とモバイルファースト
linkレスポンシブイメージはHTML(srcset)で CSSメディアクエリ担当外 画像読み込みのサイズはビューポートかボックスサイズか
上述の、単一画像伸縮によるレスポンシブではなく、ビューポートに合わせて別々の画像を表示させる仕組みが、レスポンシブイメージである
レスポンシブイメージは、CSSではなく、HTML(picture / srcset)の記述、設定した記述子(w)にしたがって指定の画像を表示させる
よって、メディアクエリ無しのブレイクポイントと言えないこともない
おもに、画像原版の複数サイズを作成しておいて、ビューポートごとに最適なサイズの画像を選択して表示させる仕組み
さらに、大画面では横長、小画面では縦長など、違う画像を指定することも可能
CSSの「object-fit」で、横長や縦長などに画像をトリミングできるが、レスポンシブイメージでは極端には実画像をトリミングした別画像を表示させることができる
DPR デバイスピクセル
レスポンシブイメージの記述子(w)は、CSSピクセルの幅ではなく、デバイスピクセルの幅を意味している
このレスポンシブイメージによって、極端には、DPR1のデスクトップよりもDPR3のスマートフォンのほうが、より大きい(横幅が広い)画像を表示することも有りとなる
よって、単一画像伸縮のレスポンシブを「レガシーレスポンシブ」と称するなら、デバイスピクセルのビューポートに合わせて画像を選択するレスポンシブイメージは「DPRレスポンシブ」とも言うべきで、今どきのRetinaなどの高解像度ディスプレイ対応なので「モダンレスポンシブ」とも表現してもいいだろう
DPR3などに対応して、スマートフォンでサイズ・容量大の画像を表示させるとは、スピードダウンにもつながりそうで、レスポンシブイメージに前のめりになることは、逆行しているおそれもありそう
まあ、Googleは「WebP」や「brotli」などを開発して、スピードとハイスペックを両立させているのだろう
されどメディアクエリ
デバイスのビューポートに合わせてコンテンツを伸縮させたり、レイアウトを変更するようなメディアクエリは、不要なのだろうか?
メディアクエリ無しがトレンド
画像のレガシーレスポンシブも含め、関数CSSや、flexbox・gridなど、世はメディアクエリ無しの方向に向かっている
GAFA(Facebook=meta抜き)も、1カラムで、ソースを見るとメディアクエリは無さそうだ
メディアクエリは便利で重宝する
さて、長々と(だらだらと)書き連ねてきたが、Web作成の現場としては、やはり、されどメディアクエリは必要であり、画面幅に応じてコンテンツを伸縮させたりレイアウトを変更するには、メディアクエリは便利で重宝する
デスクトップ サイドバーが地雷
デスクトップファーストでもデスクトップラストでも、サイドバーは無視できないほどの市民権を持っている
さらに、モバイルユーザーは100%ではなく、デスクトップユーザーもまた多く、サイトによってはほとんどがデスクトップユーザーというケースもある
メディアクエリでは、サイドバーはフッター箇所の上あたりに収められることが多い
かつ、折りたたまれているサイト(テンプレート/テーマ)がほとんど
とくにタブレットで、縦画面では折りたたみ、横画面では展開させる場合、処理のハードルがやや面倒臭い
もちろん、タップ・クリックで展開/格納もCSSで可能
余談ではあるが、格納されたサイドバー内のAdSenseは、展開されても広告が表示されないことが多く、これもひと工夫もふた工夫も要求される
モバイルファーストのメディアクエリ range syntax などの注意点
一応は、モバイルファーストのCSS記述が主流となっていると思えるが、汎用コードとスマートフォン(縦画面)専用とを区別した記述も必要
事故が少ないメディアクエリのCSS
モバイルファーストであれ、デスクトップファーストであれ、汎用コードは汎用で全デバイスで共通であり、最初のCSSを読み込んだあとで、それを書き換えるコードが割り込むことはあまり好ましくない
つまり、汎用は汎用、専用は専用と区別するべきだろう
ブレイクポイントが「600 960」の事例では
汎用は、全デバイス共通の記述で、後述のメディアクエリで書き換えしない工夫が望ましい
弊社作法では、ブレイクポイントは「600 960」にしているが、「500 850」でも何でも同じ
デバイス・ビューポート・ブレイクポイントで、CSSを仕分けするということが肝要
メディアクエリ一覧 range syntax併記
メディアクエリは、従来の冗長な max-width / min-width に対して、簡略化の比較演算子を用いた記法、Media Queries Level 4の range syntax がすべてのモダンブラウザー最新版で対応している
下記では、上段に max-width / min-width 、次の段に range syntax を併記している
- 汎用
- メディアクエリ無し
- 全デバイス共通のCSS記述
- smartphonestay_current_landscapetablet_mactablet_androiddesktop_windows
- スマートフォン縦小画面 専用
- @media screen and (max-width: 320px)
- @media (width <= 320px)
- まれに先代iPhoneSEや5の訪問者もあり
- smartphone
- スマートフォン縦画面spY 専用
- @media screen and (max-width: 600px)
- @media (width <= 600px)
- 汎用ではなくspY専用はここに
- SDO(Smartphone Display Optimization)実現には重要なメディアクエリ
- smartphone
- スマートフォン横画面spX 専用
- @media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 960px) and (orientation: landscape)
- @media (600px < width <= 960px) and (orientation: landscape)
- iPhoneのノッチ対策など、スマートフォン横画面専用のメディアクエリ
- stay_current_landscape
- スマートフォン横画面spX~デスクトップ画面dt まで 部分汎用
- @media screen and (min-width: 600px)
- @media (600px < width)
- spY以外で共通にするべきCSSはここに
- stay_current_landscapetablet_mactablet_androiddesktop_windows
- スマートフォン横画面spX / タブレット縦画面tbY 専用
- @media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 960px)
- @media (600px < width <= 960px)
- spY・tbXdt以外、つまりspX・tbYを限定するならここに
- SDO(Smartphone Display Optimization)実現には重要なメディアクエリ
- stay_current_landscapetablet_mac
- デスクトップdt / タブレット横画面tbX 専用
- @media screen and (min-width: 961px)
- @media (960px < width)
- tbX・dtで記述のボリュームもありそう
- tablet_androiddesktop_windows
spX / tbY専用の理由~PageSpeed Insights対策
CSSを1枚物にするなら、「spX / tbY」は専用ではなく、以降の dt までの汎用にするほうが都合がいい
「tbX / dt」専用を上書きできるが、「spX / tbY」の流用できる記述は「tbX / dt」では不要になる
CSSのメディアクエリはスマートフォンで不要なCSSを読み込ませないために
PageSpeed Insightsのパフォーマンス数値が低い原因、三悪はCSS・JavaScript・画像、CSSは「レンダリングを妨げるリソースの除外」「使用していない CSS の削減」などなど
WordPressテンプレート(テーマ)で採用のCSSで、とくにPageSpeed Insightsパフォーマンス向上のために、全デバイスのファーストビュー用「クリティカルCSS」を設定
メディアクエリを最適化するために、デバイス別にCSSを分離分割読み込み、スマートフォン専用とデスクトップ専用はそれぞれ、タブレットは「spY 専用」以外を読み込むようにしている
スマートフォンではメディアクエリ600以上のCSSを読み込まないのがモバイル スピードアップのポイント
range syntax (比較演算子)について
range syntax の比較演算子はつねに <=(以下) <(未満) と左向きに記述して、ブラウザーのビューポート幅が width
max-width は、ビューポート幅(width)が設定数値以下のときとなるので、比較演算子(<=)の右に数値を記述
min-width は、ビューポート幅(width)が設定数値以上のときとなるので、比較演算子(<=)の左に数値を記述など
とにかく(自分と複数制作担当者が)分かりやすいルールを決めておく
ちなみに、当サイトも range syntax のメディアクエリを実験的に採用している
表示がおかしいところがあれば、コメントをいただきたい
SDOとメディアクエリ
今どきのWeb、モダンWebでは、スマートフォン対応で、スマートフォン優先ならモバイルファーストと称されている
また、モバイルファーストで有っても無くても、パソコンというかデスクトップ対応は必須であり、モダンWebの次のミッションはレスポンシブということになる
スマートフォンとデスクトップに対応で、レスポンシブであれば、その手段でしかないメディアクエリやらブレイクポイントやら、ある意味でどうでもいいと言える
メディアクエリ・ブレイクポイントとSDO
複数のデバイスが氾濫する現状で想定するべきなのは、まずモバイルファーストではスマートフォンの縦画面と横画面のデザイン/レイアウトの切り替えに対応しなければならない
縦画面では「縦長」、横画面では「横長」という、じつはデバイス別・ディスプレイ別のレスポンシブではもっとも劇的な変化となっている
これに対して、デスクトップとタブレット横画面とスマートフォン横画面は「横長」、タブレット縦画面は縦長でも画面幅はスマートフォン横画面と同等、つまり、これら(スマートフォン縦画面以外)は「横長」として一括りで扱うことができる
ということは、スマートフォンの「縦長」「横長」をクリアできれば、他は「横長」一括として、オールクリアできることになる
SDOはスマートフォンの縦横対応でクリア
結論としては、レスポンシブはスマホの縦横をクリアすれば、モバイルのレスポンシブをクリア
さらに、これがクリアできれば、オールクリアとなる
SDOでレスポンシブSEO完全版
基本的にレスポンシブとは、同一HTMLソースで、複数のデバイス・ディスプレイに表示されることになるから、スマートフォン小画面・縦画面に表示されるソースにSEOコーディングしておけば、SEOもレスポンシブになる
つまり、スマートフォン小画面のデザイン/レイアウトで、SEOコーディングもできれば、最高最強最適のモダンWebが完成する